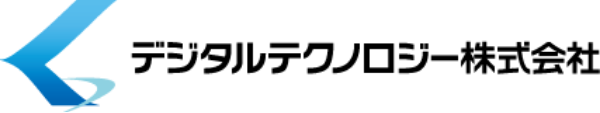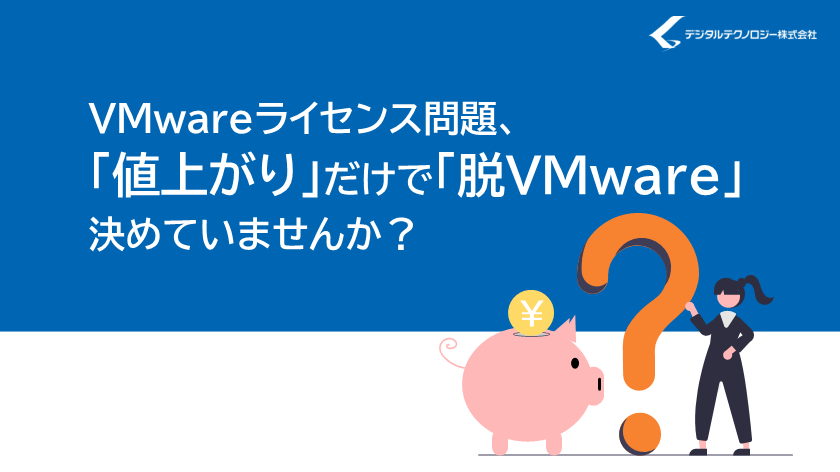
VMwareライセンス問題、「値上がり」だけで「脱VMware」決めていませんか?
※本ブログの内容は、2025年7月時点での情報に基づいております。
最新の情報については、公式サイトやお問い合わせ窓口までご確認ください。
米Broadcom社がVMware社を買収したことに伴い、ライセンス体系が大きく変更されました。この影響で、一時的にライセンスの購入ができなくなるなど、様々な問題が起こりました。
本ブログでは、ライセンス体系を改めて整理することをはじめ、「VMwareを継続する場合」「VMwareから移行する場合」どちらの場合でも、今後考えるべきことについてまとめていきます。
▼ 本ブログをもっと詳しく解説した「お役立ち資料」は以下よりダウンロードできます。
「VMware継続」を決めたものの、次に何を考えたらいいか分からない方、
VMwareから「何に・どうやって」乗り換えるか知りたい方、必見です!
\ 2025年7月版! /
目次[非表示]
- ・1.変更のあったライセンス体系を改めて解説
- ・1-1.全ての永続ライセンスは販売終息
- ・1-2.【2025年7月 更新】 SDDC(Software-Defined Data Center )製品は3つのエディションに統合
- ・1-3.【2025年7月 更新】 ユーザのセグメント分け yaaauuyu-za
- ・2. 「脱VMware」を検討する際に「追加で」考えなければいけないこと
- ・2-1.【2025年7月 更新】 旧費用・新ポートフォリオの比較
- ・2-2.「脱VMware」に心が動いた方必見!別ハイパーバイザーへの移行時の課題、確認してください!
- ・2-3.「脱VMware」or「VMware継続」の選択後・・・
- ・ 3.まとめ
1.変更のあったライセンス体系を改めて解説
1-1.全ての永続ライセンスは販売終息
2024年2月4日をもって、Perpetual(永続)ライセンスは販売終息となりました。Perpetualライセンスと新Subscriputionライセンスの違いは、下記の図の通りです。
変更ポイント!
・販売体系は、期限付きのライセンスとなります。
・課金体系は、CPU課金からCore課金となります。
・vCenterは別売りから、同梱となります。
・新Subscriptionライセンスへの移行には、ライセンスキーの入れ替えが必要となります。
1-2.【2025年7月 更新】 SDDC(Software-Defined Data Center )製品は3つのエディションに統合
新Subscriptionライセンスは下記の3つのエディションに統合されました。
・VMware Cloud Foundation
・VMware vSphere Foundation
・VMware vSphere Enterprise Plus
ライセンスのコンポーネントは下記図をご確認ください。
注意ポイント! ~ vSAN環境をご利用の方、必読です! ~
・vSANを利用する場合、VMware vSphere Foundation以上のライセンスが必要となります。
・vSANを利用する場合、容量に応じた追加ライセンスが必要です。
・2024年11月より、VMware vSphere Essentials Plusは終息となりました。
・2025年4月より、VMware vSphere Standardは終息となりました。
・ 追記 2025年5月よりVMware vSphere Enterprise plus(※)については、
Broadcom社より承認を得たCommercialユーザのみ、購入ができます。
(※)ライセンス期間は1年のみ選択可能です。
・Commercialセグメントのお客様が、新規・追加・更新にてライセンスを購入する場合、
既存契約の満了日(※) に統一する必要があります。
(※)ERP Numberに紐付いているすべての契約満了日を指します。
・全てのvSphere製品の購入および更新において、最小購入数が72ライセンスからとなります。
・1年未満の見積提示は原則不可となります。
1-3.【2025年7月 更新】 ユーザのセグメント分け yaaauuyu-za
Broadcom社によって、企業が「Strategic」「Corporate」「Commercial」のセグメントに分類されており、各セグメントで購入できるエディションが決まっています。
セグメントの判定はBroadcom社による総合判断になりますので、自社の状況を知りたい方は、当社営業担当までご連絡ください。
新ライセンス体系を改めて解説してきました。
もともとのベースライセンスの価格上昇に加えて、CPU課金であった vSAN ライセンスが容量課金となり、さらに価格を押し上げてしまっていることが「値上がり」の原因となっているのです。
2. 「脱VMware」を検討する際に「追加で」考えなければいけないこと
ライセンス変更点について改めて整理することで、「値上がり」の原因についてご理解いただけたかと思います。次に、この章では、もう少し詳細に「vSAN・3Tier」でVMwareを継続して使用する場合のライセンス価格を、新旧ライセンスを比較することで見ていきたいと思います。
また、2-2では「脱VMware」を検討する場合、ライセンス費用以外にも考慮すべき事項についてご紹介します。これは、「脱VMware」「VMware継続」の判断に大きく関わる事項ですので、事前にしっかりとご確認いただくことをおススメいたします。
2-1.【2025年7月 更新】 旧費用・新ポートフォリオの比較
以下では、「vSAN構成」と「3Tier構成」の場合に掛かるVMwareライセンス費用の試算をしています。
vSAN 4ノード(各2CPU)構成の場合、ライセンスのトータル費用は、約2.3倍となりました。
3Tier 4ノード(各2CPU)構成の場合、ライセンスのトータル費用は、約3.5倍となりました。
どちらの場合になっても、新サブスクリプションライセンスでは、ライセンス価格が増加していることがお分かりいただけたかと思います。
2-2.「脱VMware」に心が動いた方必見!別ハイパーバイザーへの移行時の課題、確認してください!
2-1で、VMwareライセンスの値上がりについてお話しましたが、ハイパーバイザーを移行する場合は様々な追加費用が発生します。
以下は、「脱VMware」を決定する際、「別ハイパーバイザーへの移行時に検討するべき事項」の一例です。検討事項を【機能面】【運用面】【移行面】に分けて記載しております。
以下のような事項についても検討済みか、今一度ご確認ください。
【 機能面 】
◆ 機能面で差異を許容できるか?
◆ 同等のセキュリティレベルを担保できるか?
【 運用面 】
◆ 運用手順の再作成
◆ 新しいインフラ基盤の技術スキルの習得は?
◆ 同じ運用チームで継続運用できるか?
◆ サーバーの設計・構築作業の再実施
◆ ネットワークの設計・構築作業の再実施
【 移行面 】
◆ 移行時にシステム停止の業務影響はでるのか?
◆ どのツールで仮想マシンを移行するのがスムーズか?
◆ そもそも既存のシステムは移行できるのか?(サポートされるのか?)
◆ 移行後のシステム動作は、誰が担保するか?
◆ 監視ツールは既存のものがそのまま流用できるのか?
◆ バックアップは既存の仕組みがそのまま流用できるのか?
2-3.「脱VMware」or「VMware継続」の選択後・・・
これまでご説明してきたように、ライセンス体系の変更によって、価格が高くなっていることが分かりました。「脱VMware」を決定するために検討する事項も上記以外にまだまだありますが、実は、単純に値上がりしているからVMwareから乗り換える、というのは危うい考えなのです。
上記の「ライセンス費用比較」や「別ハイパーバイザーへ移行する際の検討事項」をしっかり検討した結果、移行するか・継続するか、を判断するのが賢い選択だと言えます。
また、移行するか・継続するか、を決定した後にも更に検討する事項がありますので、場合別で一部ご紹介していきます。
2-3-1.「脱VMwareを決定し、乗り換えを検討されている方」
乗り換えをご検討の方は、「どこに乗り換えるのか」 「どうやって乗り換えるのか」ということを次に考えていく必要があります。
具体的に、まず、「どこに乗り換えるか」は、以下が考えられます。
◆ Windows Hyper-V
Microsoft社が提供しているハイパーバイザーです。Windows Serverの標準機能で実装できるため、Windows環境と親和性が高く、Windows VMが多い環境では費用対効果が高くなります。
◆ Nutanix AHV
HCIの先駆者、Nutanix社が提供するKVMベースのハイパーバイザーです。Nutanix HCIとAHVは緊密に連携しており、管理ツールのPrismで一元管理が可能です。
管理がシンプルなので、既存vSAN・VxRailユーザーに非常におすすめの移行先となっております。
◆ KVM系(Proxmoxなど)
完全なオープンソースであるため、ソフトウェア費用は不要です。ただ、ハードウェア・ソフトウェアの互換性の保証が限定的ということや、サポートがコミュニティベースなので、お客様側の技術力が必要になる部分は注意すべきポイントです。
「どうやって乗り換えるか」についての移行方法に関しては、実績のあるパートナーにご相談していただくことをおすすめします。当社では、システム基盤構築をはじめ、旧基盤から新基盤への移行作業も多々手掛けておりますので、お困りの際にはお気軽にご連絡ください!
▼ 「乗り換え先の候補のメリット・デメリットまとめ」や、
具体的な「VMwareから、新環境への乗り換え方法」
をご紹介した資料はこちらからダウンロードできます!
\ 2025年7月版! /
2-3-2.「VMwareを継続したままライセンス費用の上昇を抑えたい方」
当社では、VMwareを継続したまま「ライセンス費用の上昇を抑える」方法をご紹介可能です!
特に、新Subscriptionライセンスでは、課金単位がCPU数から、Core数へ変更になりましたが、この変更点が、ライセンス費用上昇の原因となってしまうケースが多いです。したがって、「必要なリソースに対して最適なCore数のCPUを選択することが、ライセンス費用の削減に繋がるのです。
また、基盤更改時に費用上昇を抑える方法は、「現状の使用状況を可視化・分析をした上で、最適なコア数のCPUを選択する事」が挙げられます。
弊社では、アセスメントツールを使用して、既存環境のリソースの可視化・分析をした上で新基盤への移行のご提案が可能です。具体的な方法については、当社までお気軽にご相談ください。
▼ アセスメントサービスを使用した、
「VMwareを継続したままライセンス費用上昇を抑える方法」
を記載した資料はこちらからダウンロードできます!
\ 2025年7月版! /
3.まとめ
本ブログに記載してきたように、実は「脱VMware」or「VMware継続」には 、ライセンスの値上がりの問題以外にも様々な検討事項があることが分かります。
上記事項をご検討いただいた上で、「脱VMware」or「VMware継続」をご判断いただくと良いかと思います!
また、移行方法についても、弊社は移行実績・長年の経験がございますので、是非お気軽にご相談ください。